ウガンダ教育スポーツ省インターンシップ報告(恩地 明日香)
2014年8月25日から10月3日までの6週間、ウガンダ教育...

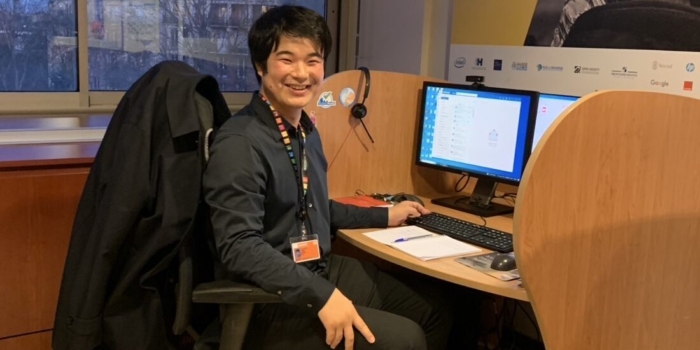
2024年10月6日から2025年4月1日まで、ユネスコ本部・健康教育課にて研修プログラムに参加しました。ユネスコ研修プログラム制度は、2024年度より開始し、文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)により促進されているプログラムです。本研修期間において、(1) 年間報告書作成に向けたMonitoring and Evaluation(M&E)の支援、(2) 教育セクター計画(ESP)における健康とウェルビーイング統合の取り組みの補助、そして (3) 各種データ活用に関する調査や分析など、多岐にわたる業務に携わりました。
 なかでも最も比重の大きかった業務は、Result Assessment Framework(RAF)2023–2025に基づく年間報告書作成の準備でした。RAFには15の指標が定められており、2024年に実施された活動をもとに、各指標の数値とその解説文を3月初旬までに取りまとめる必要がありました。まず、集計に時間を要する指標から着手し、たとえば研修を受けた教員数については、各地域オフィスの健康アドバイザーと連携し、データを収集しました。その後、教員の離職率や担当科目、生徒数などの関連情報をもとに、研修を受けた教員が担当した児童生徒数を推計し、地域別・男女別に集計しました。
なかでも最も比重の大きかった業務は、Result Assessment Framework(RAF)2023–2025に基づく年間報告書作成の準備でした。RAFには15の指標が定められており、2024年に実施された活動をもとに、各指標の数値とその解説文を3月初旬までに取りまとめる必要がありました。まず、集計に時間を要する指標から着手し、たとえば研修を受けた教員数については、各地域オフィスの健康アドバイザーと連携し、データを収集しました。その後、教員の離職率や担当科目、生徒数などの関連情報をもとに、研修を受けた教員が担当した児童生徒数を推計し、地域別・男女別に集計しました。
また、各国の政策進捗状況を、RAFで定義されている4段階(Diagnosis、Development、Adoption、Implementation)に分類し、各国がどの段階に位置しているのかを把握するとともに、2024年に実施された主要な活動を整理しました。このプロセスでは、単なる数値だけでなく、どのような支援が実施され、どれほどの関係者が関与したのかといった定量・定性的な側面を詳細に記述することが求められました。関係者とのメールのやり取りだけでは共有が難しい場面では、積極的にオンライン会議を設定し、指標の定義やインプット内容について議論を重ねました。上司からは「必要だと思えば、どの同僚にも遠慮なく連絡し、会議を開いてよい」と励まされ、主体的に動きながら、質の高い成果を目指して業務に取り組むことができました。
 教育セクター計画における健康とウェルビーイングの統合に関する取り組みは、複数の国際機関が連携するInter-Agency Group(IAG)による共同プロジェクトで、Briefing NoteやHandbookの作成、マラウイとモルディブでのパイロット・ワークショップの実施、Handbookの最終化、そしてユネスコ国際教育計画研究所(IIEP)と連携した研修プログラムの設計が行われました。私は主に、各国の教育・健康関連指標を視覚化するFactsheetの作成を担当し、Multiple Indicator Cluster Survey(MICS)、Demographic and Health Survey(DHS)、Global School-based Student Health Survey(GSHS)、Global School Health Policies and Practices Survey(G-SHPPS)などの国際調査データから必要な情報を抽出し整理しました。これらの調査は、それぞれ子どもと女性の健康や教育状況を把握する家庭調査(MICS)、保健・人口・栄養に関する包括的調査(DHS)、生徒の健康行動・心理的ウェルビーイングに関する学校調査(GSHS)、そして学校保健に関する制度・政策・実践の現状を把握する調査(G-SHPPS)です。ワークショップ自体には参加できませんでしたが、私の作成したFactsheetがグループ活動で有効に活用されたと報告を受け、大変励みになりました。
教育セクター計画における健康とウェルビーイングの統合に関する取り組みは、複数の国際機関が連携するInter-Agency Group(IAG)による共同プロジェクトで、Briefing NoteやHandbookの作成、マラウイとモルディブでのパイロット・ワークショップの実施、Handbookの最終化、そしてユネスコ国際教育計画研究所(IIEP)と連携した研修プログラムの設計が行われました。私は主に、各国の教育・健康関連指標を視覚化するFactsheetの作成を担当し、Multiple Indicator Cluster Survey(MICS)、Demographic and Health Survey(DHS)、Global School-based Student Health Survey(GSHS)、Global School Health Policies and Practices Survey(G-SHPPS)などの国際調査データから必要な情報を抽出し整理しました。これらの調査は、それぞれ子どもと女性の健康や教育状況を把握する家庭調査(MICS)、保健・人口・栄養に関する包括的調査(DHS)、生徒の健康行動・心理的ウェルビーイングに関する学校調査(GSHS)、そして学校保健に関する制度・政策・実践の現状を把握する調査(G-SHPPS)です。ワークショップ自体には参加できませんでしたが、私の作成したFactsheetがグループ活動で有効に活用されたと報告を受け、大変励みになりました。
さらに、約130カ国を対象に、教育セクター計画(ESP)の保有状況や期間、また教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE)への参加状況を整理しました。このマッピング作業を通じて、計画の変換期にある国々を特定し、今後の支援ニーズの把握に貢献できることが期待されています。また、研修終盤には、IIEP主催のLearning Design Workshopに参加し、今後の研修実施に向けた教材設計や実装方法についての議論にも加わることができました。加えて、Nutrition for Growth(N4G)サミットのサイドイベントをチームで共同主催し、これまでの取り組みを対外的に発信する機会にも恵まれました。
データ活用に関する業務では、WHOと連携して進められているGSHSデータの利活用に向けた先行研究レビューや研究課題の整理などを支援しました。教育と健康の交差点に位置するこの分野は、私の研究関心とも重なっており、知見を深める非常に貴重な経験となりました。さらに、カリキュラム・マッピング、セミナーの記録とりまとめ、ワーキンググループのマッピングなど、多岐にわたるタスクに対応しながら、進行状況や優先度に応じて業務を同時並行で進めました。
この6か月間を通じて、年間報告書の準備や国際ワークショップの支援といった重要な業務を担当させていただいたことは、大変光栄でした。常に締切を意識し、限られた時間内で成果を出すことを心がけました。また、M&Eの指標の背後には、緻密なプロセスや現場での努力があることを実感し、データの妥当性や根拠をしっかりと検証する姿勢の大切さを学びました。研修を通じて、主体的に動く力、コミュニケーション力、マルチタスクの管理能力、そして時間内に成果を出す力を実践の中で培うことができ、非常に充実した日々となりました。
 6ヶ月間私を指導してくださったAbduvahobov Parviz氏、パリにおける生活から仕事の些細なことまで教えてくださった同僚のLeonie Werner氏、共に働いた、Ibraheem Ayodeji氏、そしてユニットリーダーのHospital Xavier博士、セクションチーフのLibing Wang博士をはじめ、健康教育課の皆さまに心より感謝申し上げます。また、こうした貴重な経験ができたのも、小川ゼミ、小川先生のもとでのトレーニングと日々の学びがあったからこそだと感じています。本研修プログラムの財政的に支援して下さった公益財団法人日本国際教育支援協会にもこの場をお借りして感謝申し上げます。今後も、国際教育開発の分野で貢献できる人材として、さらなる成長を目指し、より一層努力を続けてまいります。
6ヶ月間私を指導してくださったAbduvahobov Parviz氏、パリにおける生活から仕事の些細なことまで教えてくださった同僚のLeonie Werner氏、共に働いた、Ibraheem Ayodeji氏、そしてユニットリーダーのHospital Xavier博士、セクションチーフのLibing Wang博士をはじめ、健康教育課の皆さまに心より感謝申し上げます。また、こうした貴重な経験ができたのも、小川ゼミ、小川先生のもとでのトレーニングと日々の学びがあったからこそだと感じています。本研修プログラムの財政的に支援して下さった公益財団法人日本国際教育支援協会にもこの場をお借りして感謝申し上げます。今後も、国際教育開発の分野で貢献できる人材として、さらなる成長を目指し、より一層努力を続けてまいります。
文責:宇野耕平(博士後期課程)